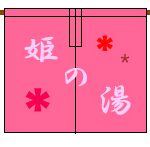暖簾と言えば、お店の入り口にかかっており、かけるだけで
風情やお店の雰囲気を伝えることができることが特徴で、言わば布の看板です。
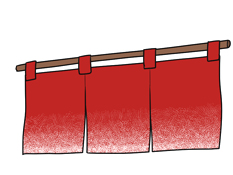
はんなりとしたやわらかい印象と歴史や風格を感じさせる佇まいを
演出することができるため、多くの店舗で利用されています。
暖簾を取り扱っているお店はたくさんありますが、伝統的なデザインや
技術、素材を用い、最新の技術も持っていると評判が良いのが京都のれんです。
京都のれんでは、オリジナルのデザインを注文することができるため、
店舗名はもちろんお店を表す言葉や柄を入れたり、グラデーションなどを
施したりすることができます。
飲食店では、暖簾を見ただけでお店で扱っている飲食物やお店の雰囲気、
こだわりなどが伝わることが大切なので暖簾でお店のPRをすることができ、
店舗入り口や窓、店舗内など活用シーンは幅広くなっています。
京都のれんは、インターネットの通販で簡単に注文をすることが
できることも特徴です。

インターネットの発注でもデザインの打ち合わせをすることができたり、
素材や色、柄などを選ぶことができるため大変便利になっています。
全国どこからでも注文が可能で、素材や製法、技法などの説明や事例も豊富です。
特注の暖簾は費用が高いというイメージがありますが、
見積もりを事前にとることができるため、予算に応じた暖簾を
制作することができることも人気の理由です。
高品質で見た目が良く、丈夫なことから全国からの注文が相次いでいます。